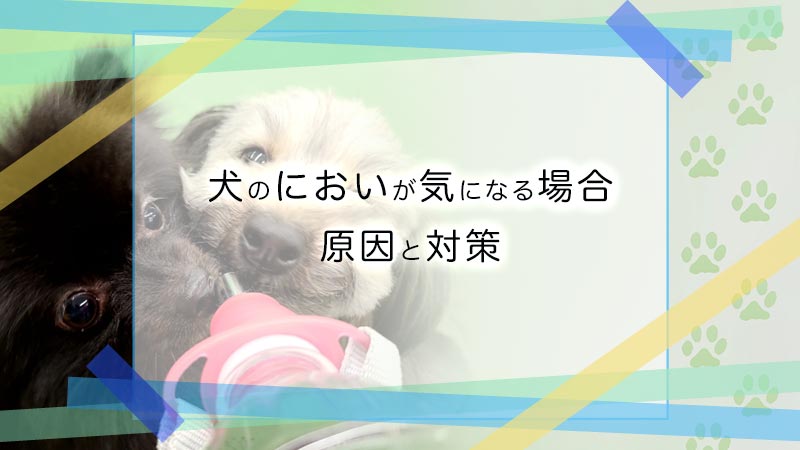犬のにおいが気になる場合の原因と対策

・犬の体臭が気になる。
・清潔にしているけどにおいがするな〜。
・においの対策教えてほしい。
こんな疑問に答えていきます。
この記事を読むと、普段から愛犬の気になるにおいをおさえたり原因を気をつけることができます。
- 体臭が気になる犬種
- 体臭の原因と対策
この後に、上の2点について詳しく解説していきます。愛犬のにおいが気になる方、においの予防をしたい方は最後までお読みください。
目次
- 体臭の原因と対策
- 汗のにおいが気になる場合の原因と対策
- 皮膚のにおいが気になる場合の原因と対策
- 口のにおいが気になる場合の原因と対策
- 便のにおいが気になる場合の原因と対策
- 肛門腺のにおいが気になる場合の原因と対策
- 尿のにおいが気になる場合の原因と対策
- 耳のにおいが気になる場合の原因と対策
- 体臭が発生しやすい犬の特徴
- 被毛が多いダブルコートの犬
- 顔にしわが多い犬
- 皮脂のにおいが強い犬
- 口臭が多い犬
- 耳のにおいが多い犬
- まとめ
犬のにおいの原因と対策

犬の体臭は皮膚や被毛からのにおい、口臭、耳臭、便臭、お尻から発生するにおいなど様々ですが、人間とは体の構造が違ったり日々のケア方法が異なったりするため、多かれ少なかれどうしてもにおいが発生してしまいます。
健康体の犬であっても体臭はしますが、あまりににおいが強い、または急ににおいが強まった場合は何かしらの病気の可能性についても考えなくてはいけません。犬の体臭の原因に応じた対策方法を中心にご紹介致しますので、愛犬のにおいで悩んでいる飼い主さんは是非ご活用ください。
汗のにおいが気になる場合の原因と対策
原因
犬にも人と同じよう、「アポクリン腺」と呼ばれる汗腺と「エクリン線」と呼ばれる汗腺がありますが、この2種類のうちにおいが発生しやすい「アポクリン腺」が犬の体のほぼ全体にあることから体臭が起こりやすくなっています。
犬の体の大部分にある「アポクリン腺」は、皮膚の内側にある皮脂を分泌するための「皮脂腺」と直結していることから、皮脂と汗が酸化して菌が繁殖することによって体臭がきつくなる傾向にあります。ちなみに犬の場合、人間のほぼ全身に分布しているにおいが少ない「エクリン線」は肉球のごく一部分にしか存在しません。
シャンプーやブラッシングの頻度が適切であるか考えましょう。
一般的には健康体の成犬であれば、シャンプーは2~3週間に1度が目安ですが、極端にシャンプー頻度が少ない、または多すぎる場合はシャンプー頻度を見直しましょう。
ブラッシングに関しては個体差によって適切な頻度は大きく異なりますが、基本的に1週間に2~3度、換毛期など時期によっては1日1回を目安にすると良いでしょう。
老犬や病気発症中の犬でシャンプーによって体に負担がかかる場合は、シャンプータオルやぬるま湯で濡らしたタオルなどを利用して定期的に体を拭くことをおすすめします。
皮膚のにおいが気になる場合の原因と対策
原因
不衛生な環境下で生活していたりシャンプーを怠ったりしていると、皮膚から発生するにおいが強まります。犬は人のように毎日お風呂に入るということがないうえ、ほぼ全身が被毛で覆われていることからにおいがこもりやすいので注意が必要です。
その他、急ににおいがきつくなるような場合は「脂漏症」や「膿皮症」、「マラセチア」などの皮膚疾患の可能性を考え、顔だけ部分的に臭う場合は「涙やけ」が起こっていないかにも注意が必要です。
におい以外に皮膚の乾燥、炎症や痒み、出来物など何かしらの症状がある場合は動物病院で検査を行い病気の根本的治療を行いましょう。
汗や皮脂が原因のケース同様、シャンプーやブラッシング頻度の見直しも大切ですが、皮膚が乾燥している場合は犬用保湿ローションを活用するのも効果的です。
口のにおいが気になる場合の原因と対策
原因
犬の口臭の原因でとても多いのが歯周病によるにおいです。歯周病になり、歯肉炎や歯周炎が悪化することから口腔内の様々な部位で炎症が起きて口臭の原因になります。
その他、病気でなくても歯垢が多かったり水分摂取量が少なかったりすると、においが強まることがあります。口臭の原因は口腔内の病気にとどまらず、内臓の病気や胃腸の不具合・疾患が原因で引き起こされることもあるので注意が必要です。
におい以外に口腔内に歯石や炎症、出来物など何かしらの症状がある場合、または下痢や便秘など何かしらの消化器系症状が出ている場合は、動物病院で検査を行い病気の根本的治療を行いましょう。
口腔内の病気が原因でない場合、こまめに新鮮な水を飲ませて様子を見ると良いでしょう。
便のにおいが気になる場合の原因と対策
原因
便は健康体の犬であっても通常きつい便臭を発生しますが、食べ物が原因でにおいが強まることがあります。便臭がきつくなる食べ物が犬の体に害を及ぼすわけではありませんが、下痢や軟便によってにおいが強まる場合は胃腸障害や何かしらの病気を疑う必要があります。
下痢や便秘、嘔吐など何かしらの消化器系症状がない場合は、食事内容を変えて様子を見ると良いでしょう。
トウモロコシや米類など穀物の割合が多いドッグフードに関しては、未消化物が増えることから便臭が強まる傾向にあるので、その場合は良質な動物性たんぱく質が主成分の消化しやすいドッグフードを試してみるのも効果的です。
便に何かしらの問題がある場合は、動物病院でしっかりと検査して原因に応じた治療を行います。
肛門腺のにおいが気になる場合の原因と対策
原因
一般的に犬の肛門腺内の分泌液は便と一緒に排泄されますが、小型犬や老犬、病気を発症している犬をはじめとし分泌液である「肛門嚢」が溜まってしまいにおいがすることがあります。
動物病院やトリミングサロンで肛門腺を絞ってもらいましょう。
肛門腺絞りは慣れてしまえば自宅で簡単にできるので、はじめは動物病院などで処置してもらうときに見学させてもらうと参考になります。
尿のにおいが気になる場合の原因と対策
原因
尿臭は主に水分不足によって尿が濃くなった場合に強まり、アンモニア臭の独特なにおいがするようになります。病気の可能性としては、細菌性膀胱炎、腎性尿糖、重度の糖尿病などが考えられますが、糖尿病の悪化が原因で低血糖が引き起こされている場合、甘酸っぱいような「ケトン臭」が引き起こされることもあります。
まずは水分摂取量を確認し、必要に応じて強制的に水分をこまめに摂らせましょう。
水を与えても飲まない場合は、ヤギミルクや無調整豆乳、少量の低塩チーズを水分に加えるなど嗜好性が高まる工夫をしましょう。
病気の可能性がある犬の場合は、獣医師の指示に従い適切な治療を受けましょう。
耳のにおいが気になる場合の原因と対策
原因
耳からにおいが発生する場合は、内部に耳垢や汚れ、細菌が発生している他、外耳炎や中耳炎、内耳炎の病気の可能性もあります。
定期的な耳掃除が効果的ですが、犬の耳は複雑な構造になっているので慣れていない場合は動物病院で耳掃除をしてもらうことをおすすめします。
過度な耳掃除や適切に処置できない場合、耳の内部を傷つけてしまい、傷や炎症の原因になるので耳の検査と一緒に動物病院で適切な処置をしてもらいましょう。
体臭が発生しやすい犬の特徴

被毛が多いダブルコートの犬
ダブルコートの犬種は被毛が多いことから、ほこりや菌が付着しやすくにおいがこもりやすいと考えられます。柴犬、ラブラドール、フレンチブルドッグ、チワワ、ゴールデンレトリバーなどが一例として挙げられます。
顔にしわが多い犬
ブルドッグ、フレンチブルドッグ、パグ、シャーペイ、ブルマスチフなど顔にしわが多い犬の場合、しわの間の汚れや細菌などが原因でにおいが発生しやすいと考えられます。
皮脂のにおいが強い犬
アメリカンコッカースパニエルやシーズーなどは皮膚に脂が生じやすく、体臭が目立つことがあります。
口臭が多い犬
口臭は犬種でなく年齢で差が生じやすく、3歳を超えたあたりから目立ちはじめて歳をとるにつれにおいが強まる傾向にあります。口臭の1つとしてよだれに着目するのであれば、ニューファンドランドやセントバーナードなどが一例として挙げられます。
耳のにおいが多い犬
アフガンハウンド、イングリッシュスプリンガースパニエル、キャバリア、ゴールデンレトリバー、バーニーズマウンテンドッグなど垂れ耳の犬は耳垢や菌が溜まりやすく、耳のにおいが発生しやすいと考えられます。
まとめ
犬の体臭は原因によって対処法が様々であり、まずは何故においが発生するのかを考えて原因に応じて対処しなければいけません。病気でない場合は、食事やシャンプー、ブラッシングや衛生面の管理など自宅でできるにおい対策が多いので、是非試してみてください。
 わんわん小型犬動物学校
わんわん小型犬動物学校