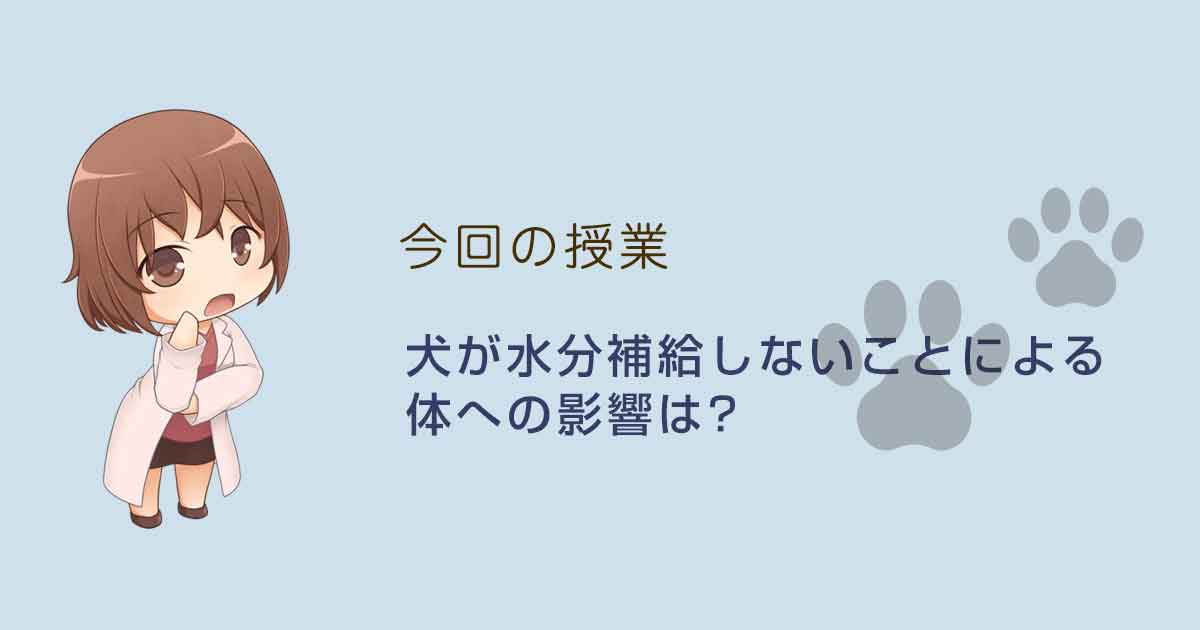犬が水分補給しないことによる体への影響は
人の体は70%水でできているなんていうよね。
人にとっても犬にとってもお水は大切なんじゃ。今回は水を飲まない犬の体に与える影響についてじゃ。
お水を飲んでくれないと心配になるわ。
お水を飲んでもらうにためにも工夫が必要なんじゃ。
お水に関する疑問が多いので説明するわ。
人間同様に犬にとっても水分補給は何より大切な体を維持するための栄養源です。
犬の体の約60%~70%程度が水分でできていると言われていますが、実はそのうちの約10%程度の割合で水分量が減少すると、体に様々な支障をきたす脱水症状が引き起こされる可能性があります。
今回は、犬にとって水分補給が大切な理由や必要な水分量、上手な水分補給のさせ方など幅広くご紹介させていただきますので、犬が水を飲まなくて困っている飼い主さんは是非参考にしてください。
犬に水分補給が大切な理由

犬の体の約60%~70%が水分
犬の年齢や状態によって個体差はあるものの、基本的には犬の体の約60%~70%程度が水分でできていると言われているため、人間同様に犬にとっても適切な水分補給は生きていく上で欠かすことができません。
水分とは厳密にいうと犬にとってのエネルギーに変わることはありませんが、栄養素の中では一番重要であると言われています。
犬の体温調節には水が必要
犬の体内の熱を体外に放出するために水は非常に重要であり、犬の体温調節には水はなくてはならない栄養素です。
犬の体内の水分は、尿として排泄される以外に呼吸器官や皮膚から蒸発されますが、この時に水分を蒸発させるためにたくさんの熱量が必要になります。
少量の水分であっても体外に水を蒸発させるためには多くの熱量が必要なため、犬の体内に水分があることによって体の熱を放出できる仕組みになっています。
水分が犬の栄養素を運ぶ
水分は直接的な犬のエネルギー源には変わりませんが、様々な栄養素を体内に運ぶ、または不要な物質を体外に排出するのには必要不可欠な栄養素です。
食事で摂取した栄養素は水分によって体内に運ばれ、不要な物質は水分によって便や尿として体外に排出されます。
水分が欠乏すると栄養素の消化や犬の体に溜まる不要な老廃物排出ができなくなるため、十分な水分量が体内にないと犬の体は正常に機能しなくなります。
水分によって関節部分や眼球が機能する
水分は犬の体の関節部分の軟骨の動きや眼球の動きに大きく関係しており、これらは適切な水分があるために円滑に動くようになっています。
体内の化学反応には水分が必要
犬の体内では、加水分解(水が作用することによって起こる分解)を中心に様々な化学反応が起こっており、栄養素であるタンパク質や炭水化物、脂肪などの酵素の消化には必須であるため欠乏してしまうと、これらの化学反応に支障をきたします。
個々の犬に必要な水分量を知るには?

健康体の犬であれば犬が自ら摂取する水分量が適量
通常、健康体の犬の場合は犬が自ら摂取する水分量で1日の水分は足りるようになっています。
健康体でしっかり水分補給が出来ている場合は、犬の生活空間に常に新鮮な水を置いておきましょう。
しかしながら、病気や老衰など何かしらの理由で水分摂取が自らできない犬の場合、またはもともと水分をあまり摂らない犬で脱水症状が見られる犬の場合は人の手で水を与えなくてはいけません。
計算機で計算できる正確な必要水分量の計算方法
何かしらの理由で自ら水分補給ができない犬の場合は、飼い主さんがこまめに犬に水分を与えなければいけません。
そんな時に、水分量が足りていないのではないかと不安な場合は、計算機で犬に必要な1日の水分量目安を計算することができます。
1日の水分量の計算方法
- ①まずは犬が安静にしている時のエネルギー要求量を求めよう!
- ★求め方=体重×体重×体重=√√×70
体重5㎏の犬で考えると⇒「5×5×5=√√×70」を計算機で計算すると、結果が234.059・・・
⇒犬が安静にしている時のエネルギー要求量は約234kcal
- ②次に犬に必要な1日のエネルギー要求量を確認しよう!
- ★求め方=①(犬が安静にしている時のエネルギー要求量)の計算結果 x 係数
★係数は犬の状態別で異なるため、下記の中から犬に合った係数を選ぶ -
係数 状態 3.0 月年齢4か月以前の子犬 2.0 月年齢5か月~9か月の子犬 1.8 避妊手術をしていない成犬 1.6 運動量が成犬時と変わらない老犬 1.6 避妊手術をしている成犬 1.4 運動量が減っている老犬 1.4 肥満気味の成犬 1.0 肥満で減量が必要な犬 4.0 年齢問わず運動量が多い犬 5.0-7.0 年齢問わず運動量が非常に多い犬 ⇒「体重5㎏」の「避妊手術をしている成犬」の場合⇒①の安静にしている時のエネルギー要求量「234」 x 係数「1.6」=374.4
- ③ ②で計算した1日に必要なエネルギー量が1日に必要な水分量とほぼ同値になるため、「体重5㎏」の「避妊手術をしている成犬」の場合は1日に必要な水分量は約「374.4㎖」
- ただしこれはあくまで目安計算であり、犬の年齢や状態、個体差、季節、また排泄状態や排尿回数によって必要な水分量は多少異なります。
自分で計算するのが面倒な場合は、上記の係数だけ分かれば犬の体重と係数を入力するだけで1日のエネルギー要求量(=水分量)が計算できるサイトもあるので活用しましょう。
犬が水分補給をしない原因とは?

シニア期の犬は水分補給が苦手
シニア期に入った老犬の場合、体の代謝機能が低下することによって水分補給量が減ることがあります。
また、加齢によってあまり動かない犬については水分補給をすること自体が面倒になっている可能性もあるため注意が必要です。
季節による一時的な原因
冬の寒い時期は犬の体温が上がりにくいため代謝機能も低下することから、必然的に犬の水分補給量も夏場に比べて減る傾向にあります。
体の不調が原因
犬は体の具合が悪い時にも水分補給量が低下することがあり、特に吐き気を伴いやすい消化器系症状が現れている場合は水分を摂りたがらないので注意が必要です。
その他にも口腔内の病気(口内炎、歯周病、歯肉炎など)によって、水を口に入れることを拒み水分補給の量が低下する場合もあります。
犬に水分補給をさせるための方法
水分量の多い食事に切り替える
水分補給が苦手な犬、または病気や老化など何かしらの理由で水分を自ら頻繁に摂ることができない犬の場合は、食事に水分を含ませると良いでしょう。
ドライフードを与えている場合は、水分量が多いウェットフードやセミウェットフードに変更する、ドライフードをそのまま与えたい場合はぬるま湯でフードをふやかして与えると良いでしょう。
ただし、犬の食事は通常2回~3回程度と小数回ですので食事以外でもこまめに水分補給をさせてあげる必要があります。
水分に犬が好きな香りを加える
どうしても水を飲まない場合は、ヤギミルクや無調整豆乳などを水に混ぜるなど犬の嗜好性が上がるような工夫をすると良いでしょう。
肉が好きな犬の場合は肉を茹でて出汁を使用するなど、犬の好物となる香りを水分に加えてあげると飲むようになる犬が多くいます。
給水用品を利用する
時々置いてある水には興味を示さず水道から流れる水を好んで飲む犬がいます。そのような場合は常に水が流れる仕組みになっている循環給水機を利用すると良いでしょう。
水分補給しやすい状態にしてあげる
老犬や何かしらの病気により肉体的に体力がない犬の場合、水の置き場所が寝床から遠い場合や器の位置が低すぎるなどのちょっとした理由で水分補給を怠ってしまうことがあります。
犬の体の状況に合わせて水飲み場を考えてあげることが大切です。
また、これらの理由により気管や気管付近の筋肉が弱っている犬の場合、床に直接水飲みを置いてしまうとむせてしまうことがあり危険ですので、水置き場の高さ調整をしてあげましょう。
基本的には、水や食事は犬の肩付近の高さにくるように設置してあげることが好ましいと言われていますので、高さ調整ができる犬用食器テーブルなどを活用するのも良いでしょう。
頻繁に水を変えてあげる
犬の健康面を考えても常に新鮮な水を準備してあげることが好ましいと言えますが、神経質な犬の場合は古い水を飲まない場合もあります。
匂いの種類や個体差によって異なりますが、犬の嗅覚は人間の1000倍~1億倍程度であると言われていますので1日最低でも2回は新鮮な水に変えてあげましょう。
犬にミネラルウォーターを与えても大丈夫?

多くの飼い主さんが疑問を感じているミネラルウォーターですが、犬の水分補給には基本的には過剰にミネラル分が含まれていない水道水が好ましいと言えます。
ミネラルウォーターは大きく分けて軟水と硬水の2種類がありますが、どうしてもミネラルウォーターを与えたい場合、硬水はストルバイト結石になりやすいと言われているため軟水を選択すると良いでしょう。
硬水は少し与えたからといってストルバイト結石を発症するわけではありませんが、長期的に与えることによって結石ができる可能性を少なからず増やしてしまうので避けた方が良いと言われています。
体質によってストルバイト結石ができやすい犬の場合は特に硬水は避けた方が良いでしょう。
また、都心部などのカルキ臭がする水道水にどうしても不安がある飼い主さんについては浄水器を利用すると良いですね。
犬の水分補給について幅広くご紹介致しましたが、犬の生命にとって水は一番大切な栄養素であり水分補給ができないと脱水症状を引き起こして最悪の場合は死に至ることもあります。
老衰や何かしらの病気によって十分な水分補給が出来ない犬や、もともと水分補給をこまめにしない犬の場合は、犬がしっかりと水分補給できるように工夫してあげなくてはいけません。
日頃から犬がしっかりと水分補給をしているか頻繁に確認してあげましょう。
うちのマロンは浄水器のお水を飲んでおるぞ。
ちゃんとお水とりかえてあげてね。博士はズボラそうだわ。
それがなかなかマメなんじゃい。マメ博士と呼ぼれとるぞ。
え?何いまのは。つまらないギャグ?
 わんわん小型犬動物学校
わんわん小型犬動物学校