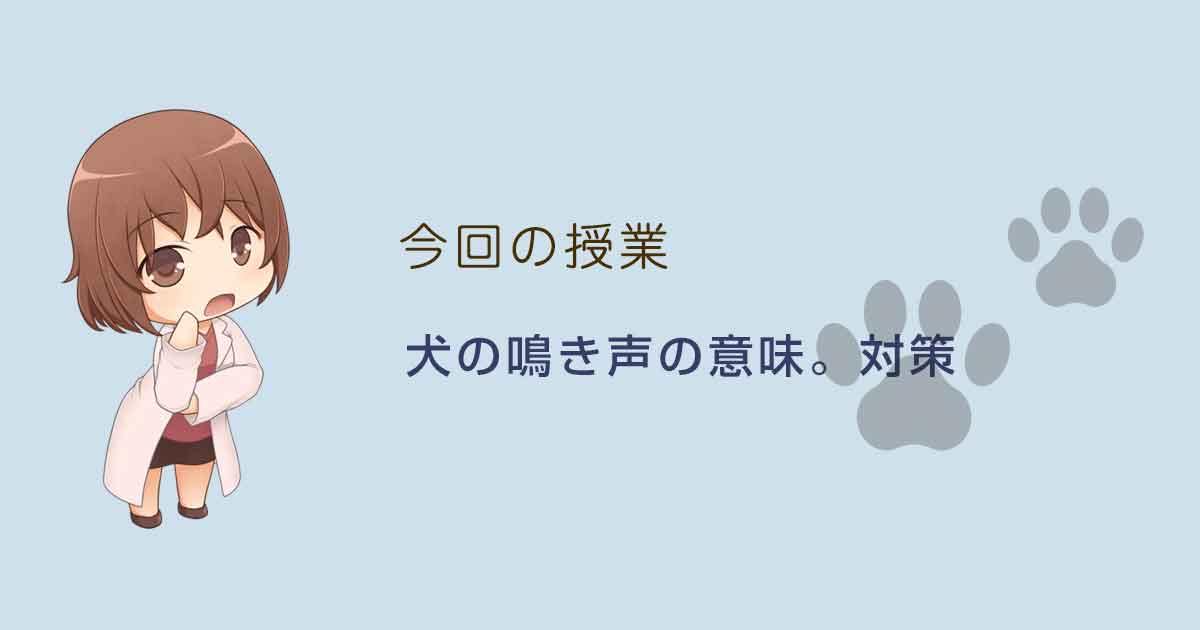犬の鳴き声の意味。対策
人は言葉を用いて気持ちや考えを自由に伝えることができますが、犬は言葉を使えません。代わりに鳴き声を発して、飼い主さんに向かって訴えかけます。
犬の鳴き声の意味が分かればより愛犬との絆も深まるはず。そして、無駄吠えを止めさせられれば、ご近所へ迷惑が掛かるなどのトラブルも避けられます。
そこで今回は犬の鳴き声の意味と対策について説明していきます。
犬が鳴くのは仕事だという飼い主がおるな。
仕事ではないわ。それは人間の赤ちゃんのこと。飼い主はきちんと犬の鳴き声を聞いて理解する必要があるの。
ほう。最近わかってきたの〜
博士のお陰。最近は病院でもバイトはじめたからわかるようになってきたわ。
がんばりたまえ!
なんか、えらそうだわ。
犬の鳴き方の違い

犬は鳴いて伝えると言いましたが、ひとくちに「鳴く」といっても様々な気持ちを表現するために方法や伝え方を変えて鳴き声を発します。
これをある程度理解できれば、愛犬がなぜ鳴いているのか分かってあげることができるでしょう。愛犬が鳴いている時には、次にご紹介するポイントによく注目してみてください。その時々で違いがあることが分かるはずです。
- 声の大きさ
- 間隔や回数
- 長さ
- 声の高さ
犬はこれらを使い分けたり、あるいは組み合わせたりして、気持ちの伝え方を変えています。
犬の鳴き声の種類

嬉しさ、悲しさ、欲求、痛み、怒りなど様々な気持ちを伝えるために、鳴き声を発する犬たち。先程お伝えした組み合わせ方によって、ある程度どのようなことを訴えたいのか理解することができます。
個体差もあるので一概には言えませんが、犬の鳴き方で分かる一般的な犬の気持ちをご説明します。
「ワンワン」と大きな声で鳴く
一番よく耳にする鳴き声が「ワンワン」というものではないでしょうか。大きな声で短く繰り返し吠えている場合には、主に次の3つの気持ちを表現しています。
- 要求
- 警戒
- 興奮
なんらかの要求がある時や主張がある時にこのように吠えます。また、お客さんが来たり、他人の犬に会ったりして、警戒心を表現していることもあるでしょう。
さらに遊びたい時や飼い主さんを呼んでいる時などの興奮状態なども挙げられます。
「キャン!」と短く鳴く
高い声で短く鳴いた時は、どこかケガをしていたり痛かったりといったことを表している場合があります。ケガや痛みの元となるものがないか確認してあげましょう。
また、驚いた時にも「キャン!」と声を出すことがあります。
「クンクン、キューン」と心細そうに鳴く
これらの表現をしている時は、「寂しい」や「不安」な気持ちを表していることが多いでしょう。留守番の前に寂しかったり、飼い主さんに甘えたかったりする時の鳴き声だと考えられます。
また、どこかが痛いといったケースもあるので、愛犬の態度や表情をよく観察しましょう。
低音で「ウゥー」と唸る
犬が低い声を出すのは、威嚇しているケースがほとんどです。「ウー」と唸ったり、「ガルルル」といった低い声を継続して出します。
他人や他人の犬に対して警戒し、近づくなという合図でもあります。稀に遊んでいてテンションが上がっている時に、おもちゃを取られそうになったりすると、こうした声を出すこともあります。
特に牙を剥き出しにしている時は、攻撃寸前ですのでそれ以上刺激させないようにし、噛みつかないよう制御しなければなりません。
「ワオーン」と鳴く
遠吠えは犬の祖先がオオカミであったことの名残です。オオカミは遠吠えを用いて、遠くの仲間とコミュニケーションをとっていました。
現代の犬たちは、サイレンの音などに反応し遠吠えをすることがあります。仲間とのコミュニケーションのために使用していた行動をするということは、「寂しい」といった気持ちを持っているケースもあります。
頻繁にしているようであれば、普段の愛犬の様子をよくみていてあげてくださいね。
「ワウワウワウ」と鳴く
喉元に籠ったような声で連続してこうした鳴き声を出す時には、なんらかの異常を伝えようとしているサインです。
犬の無駄吠えとは

よく「犬が無駄吠えをして困る」といった悩みを聞くことがあります。ですが、犬は吠えることでしか気持ちを伝達できません。ですから、吠えるのは当然であり、無駄なことではないのです。
とはいえ、あまりに鳴いてご近所から苦情を受けても困りますよね。最悪の場合、引っ越しをしなければならなくなったり、手放さなければいけなくなったりしかねません。
無駄吠えの原因のなかで特に許容範囲を越えて、気になってしまうのが、欲求や縄張り意識によるものではないでしょうか。
- 遊んで欲しい
- ごはんが欲しい
- 散歩に行きたい
- 留守番をしたくない
- 来客が来た
- チャイムが鳴った
- 外から声がした
これらのような日常の出来事で度々けたたましく吠えられては、少し参ってしまいます。
さらに、環境省では「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」において、騒音や糞尿の放置などによって近隣住民に迷惑をかけてはいけないという決まりがあります。
ですから飼い主さんには、愛犬がなぜ鳴いているのかを理解し、日頃からしつけたり、無駄吠えをさせないように努める義務があるのです。
犬の鳴き声の対策

ではどのように対策するのが良いのでしょうか。しつけには根気が必要ですが、次のような方法を試してみて、なるべくご近所トラブルを回避できるよう心掛けましょう。
欲求を満たす
まず一つに犬の欲求を満たすという選択肢があります。犬はなんらかの欲求があり吠えていることが多いものです。
そこで、きちんとした飼育環境に置かれているかを再度確認してみましょう。食事量、散歩量、犬に適した温度、衛生管理などがきちんと満たされていない場合に吠えるのはある意味当然の権利と言えますよね。
根本的な原因がある場合には、犬の欲求をきちんと満たしてあげれば収めることができることもあります。
我慢させる
きちんとした飼育環境にあるのに吠えている場合には、それ以上を欲求している無駄吠えと言えます。そのような場合には我慢をさせることが有効的。
鳴いている時に欲求を満たしてしまうと、犬は鳴けば欲求が満たされる、思い通りにしてもらえると学習します。
そうなってしまうと主従関係にも影響してきますので、不当な欲求には答えないことがベストです。無駄吠えをしているときには、徹底的に無視をするのが一番有効的。
大きい声で叱ったりすると余計にヒートアップしてしまうので注意が必要です。
鳴き止むことができたら褒めたりごほうびをあげましょう。これを繰り返すと、犬は吠えなければ良いことがあると覚えてくれるはずです。
フォーマットトレーニングを行う
フォーマットトレーニングを行うことも有効的です。フォーマットトレーニングとは犬の状態を初期化すること。
アイコンタクトや「お座り」・「待て」、などを基本動作とし、問題行動を起こしたときにこれらの指示を出すことでフォーマット(初期の状態に)し、問題行動をストップさせるトレーニングです。
無駄吠え以外にも、愛犬をコントロールするのに役立ちますのでぜひ、日頃からトレーニングしておくと良いですね。
犬の鳴き方のまとめ
犬が吠えるのは当然のことです。それは何かを伝えたいという表れです。そこにはケガや病気などを知らせる重要なヒントが隠れている場合もあります。
ですが、あまりに度が過ぎるとご近所迷惑にもなり、飼い主さんのストレスにもなってしまうでしょう。
犬の心の中まで覗くことはできないので、必ずしもこの鳴き方はこういうことだ、とは言えませんが、ある程度理解しておくことで愛犬の気持ちを分かってあげられるはずです。
そして、ときにはそれを満たしてあげ、ときにはしつけ、良い関係を築いてくださいね。
 わんわん小型犬動物学校
わんわん小型犬動物学校